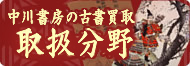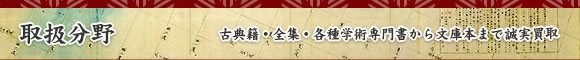
落語ほか古典芸能関係の古書を大量出張買取いたしました
『日本の芸談 全8冊』『落語選集 全15冊』『落語名作全集 全7冊』『落語寄席風俗誌』『寄席芸人伝 全11冊』ほか落語を中心に古典芸能関係の古書2000冊を出張にて大量買取りさせていただきました。大切にされていたたくさんの蔵書をお譲りいただき誠にありがとうございました。
- 出張買取
- 2025年2月15日
| 地 域 | 千葉松戸市 |
|---|---|
| 買取分野 |
【商品詳細】
『わたしの寄席』安藤鶴夫 雪華社
『日本の芸談 全8冊』九藝出版
『落語寄席風俗誌』林家正蔵・坊野寿山 展望社
『芸人紙風船』木下華声 大陸書房

『らくご小僧』立川志らく 新潮社
『落語で江戸を聴く』槇野修 PHP研究所
『林家正蔵 全3冊』青蛙房
『落語選集 全15冊』今村信雄編著 西澤道書舗

『寄席放浪記』色川武大 廣済堂出版
『金馬のいななき』三遊亭金馬 朝日新聞社
『談志人生全集 全3冊』立川談志 講談社
『定本 艶笑落語(全)』小島貞二編 立風書房

『定本 落語名作全集 上下2冊』小島貞二編 立風書房
『現代落語事典』光風社
『志ん生のいる風景』矢野誠一 青蛙房
『落語長屋の知恵』矢野誠一 青蛙房

『現代落語家論 上下2冊』川戸貞吉 弘文出版
『寄席芸人伝 全11冊』小学館
『古典落語と落語家たち』興津要 参玄社
『桂三枝という生き方』桂枝雀 ぴあ

『上方笑芸見聞録』長沖一 九芸出版
『談志楽屋噺』立川談志 白夜書房
『愉しい落語』山本進 草思社
『志ん朝と上方』岡本和明 アスペクト

『米朝落語全集 全8冊』創元社
『初代桂春団治落語集』東使英夫 講談社
『笑芸人 創刊号~』白夜書房
『上方落語家名鑑 ぷらす上方噺』やまだりよこ 出版文化社

『談志絶倒昭和落語家伝』立川談志 大和書房
『口演速記 明治大正落語集成 全7冊』講談社
『絵本・落語風土記』江國滋 青蛙房
『三遊亭円朝の遺言』藤浦敦 新人物往来社

『談志最後の落語論』立川談志 梧桐書院
『上方芸能列伝』澤田隆治 文藝春秋
『落語の種あかし』中込重明 岩波書店
『落語と私』桂米朝 ポプラ社

『落語の黄金時代』山本進他 三省堂
『江戸前で笑いたい』高田文夫編 筑摩書房
『十代文冶 噺家のかたち』桂文冶 太田博編 うなぎ書房
『とことん楽しむ 落語のすべて』TBS落語研究会編 日本文芸社

『福耳落語』三宮麻由子 日本放送出版協会
『落語の世界 全3冊』延広真治他 岩波書店
『落語俗物園』榎本滋民 扶桑社
『落語的学問のすすめ 全2冊』桂文珍 潮出版社

『落語 長屋の四季』矢野誠一 読売新聞社
『文人たちの寄席』矢野誠一 白水社
『文句と御託 談志ひとり会』立川談志 講談社
『落語名作全集 全7冊』立風書房

『落語のレトリック』野村雅昭 平凡社
『わが落語鑑賞』安藤鶴夫 筑摩書房
『落語家論』柳家小三治 新しい芸能研究室
『真二つ 落語作品集』山田洋次 大和書房

『哲学的落語家!』平岡正明 筑摩書房
『シュルレアリスム落語宣言』平岡正明 白夜書房
『志ん生芸談』古今亭志ん生 河出書房新社
『米朝・上岡が語る昭和上方漫才』桂米朝・上岡龍太郎 朝日新聞社

『落語博物誌』京須偕充 弘文出版
『上方落語はどこへゆく』桂福団治 海風社
『小沢昭一がめぐる寄席の世界』小沢昭一 朝日新聞社
『落語ことば辞典 江戸時代をよむ』榎本滋民・京須偕充編 岩波書店

『文楽でございます』武井加津子 ゴマブックス
『歌舞伎音楽を知る』西川浩平 ヤマハミュージックメディア、
『歌右衛門伝説』渡辺保 新潮
『私説コメディアン史』澤田隆治 白水社
落語など古典芸能に関する古書は老若男女問わず愛好家から人気があります
近世以前に始まり今なお伝承されている演劇・音楽・舞踊・演芸などの大衆芸能のことを古典芸能といい、歌舞伎・能楽・浄瑠璃・文楽・雅楽・神楽・日本舞踊・講談・浪曲・落語と様々な分野が挙げられます。
その中で江戸時代に成立した落語は日本の伝統的な話芸のひとつです。噺の最後に「落ち」または「下げ」がつき、扇子や手ぬぐいを小道具にして身ぶり手ぶりのみ、声色や表情で何役も演じることが特徴です。舞台も歌舞伎や浄瑠璃など他の古典芸能のような大がかりな設備ではなく、客席より一段高く設けた高座と呼ばれる場所に座布団を置いて座ることが一般的です。
落語の起源は戦国時代、将軍や大名に仕え話し相手となっていた「御伽衆(おとぎしゅう)」だと考えられています。御伽衆は書物の講釈といった教養だけでなく武勇伝や武功話などを話術の巧みさを活かして語り、特に豊臣秀吉の御伽衆であった山名禅高や曽呂利新左衛門らは噺家の祖とも言われています。
江戸時代に入ると滑稽な話を集めた『醒睡笑』が僧侶の安楽庵策伝によって編纂され、のちの落語や小咄集にに多大な影響を与えました。元禄期、上方(京・大坂)と江戸においてほぼ同時期に落語は成立したとされており、当時は「落語」という呼称ではなく、上方では町の辻や寺社の境内で聞かせていたことから「辻噺」、江戸では芝居小屋など様々な屋敷で演じていたことから「座敷噺」と呼ばれていました。
その後、初代桂文治や初代三笑亭可楽をはじめとする落語家が誕生し聴衆を集め噺を語る場所が設けられるようになります。これはやがて「寄せ」「寄せ場」と呼ばれるようになり庶民の娯楽の場として大きく発展し、隆盛期には江戸に125もの寄席が存在し初代三遊亭圓生、初代林屋正蔵といった落語家が活躍し様々な演目が上演されました。
幕末から明治時代にかけては「近代落語の祖」として落語界の大名人と称される三遊亭圓朝が登場し、落語だけでなく文学の分野や言文一致運動にも影響を及ぼしました。明治36年(1903)には初めてレコード録音が行われ、ラジオ放送が始まった大正14年(1925)以降はラジオで落語を聴けるようになるなど、人々が気軽に落語を楽しむことができるようになっていきました。なお、この頃から「落語」という呼称が定着していったと言われています。
近年では落語を題材にしたドラマ・映画・漫画・アニメなども多く、老若男女問わず落語に興味を持つ方が増えています。気軽に行くことができる落語会や寄席公演なども多く、関連書籍は落語家から愛好家まで幅広い方から需要があります。また日本の古典芸能は海外の方からも高い人気を誇っており、国内外問わず喜ばれる書籍となっています。お手元に整理や売却をお考えの落語に関する古書がございましたらお気軽にお問い合わせください。
愛書館中川書房では『講談落語集』『昭和落語名作選集』『東都噺家系図』『むかしの寄席』『咄本よりみたる近世初期言語の研究』『隨録三遊亭圓朝 正続2冊』ほか落語など古典芸能に関する古書の出張買取を承っております。
以前には『名人落語傑作集』『上方落語寄席囃子の世界』『落語名作揃』『寄席文字字典』『円朝人情噺』などの古書を出張にて買取りさせていただきました。
落語など古典芸能関係の買取事例については「古今東西 落語家事典ほか古典芸能関係の古本を出張買取いたしました」「『歌舞伎俳優 二代目 中村吉右衛門 特別愛蔵版』の古本を出張買取いたしました」なども合わせてご覧ください。
【当店取扱商品】

書名:噺の運び 寄席えっせい集 限定版
著者:麻生芳伸 金原亭馬生・絵
出版社:紅
発行年:昭和49年(1974)

書名:金原亭馬生集成 全3冊
著者:藤井宗哲編
出版社:旺国社
発行年:昭和51年(1976)

書名:志ん朝の落語 全6冊
著者:古今亭志ん朝 京須偕充編
出版社:筑摩書房
発行年:平成15年(2003)
落語ほか歌舞伎・能・狂言・雅楽ほか日本の古典芸能に関する古書の買取強化中!
このほか愛書館中川書房では『江戸歌舞伎法令集成 全3冊』『能・狂言研究 中世文芸論考』『人形芝居と近松の浄瑠璃』『文楽首の研究』『宝生流舞の囃子集』『日本浪曲史』など落語・浪曲・講談・雅楽・浄瑠璃・文楽・歌舞伎・能・狂言といった日本の様々な古典芸能に関する古書の出張買取も承っております。
『江戸中期上方歌舞伎囃子方と音楽』『狂言歌謡研究集成』『能の囃子と演出』『浄瑠璃本史研究 近松・義太夫から昭和の文楽まで』『中世芸能の研究 呪師・田楽・猿楽』『日本舞踊全集 全8冊』などお手元に気になる品がありましたらお気軽にご相談ください。

書名:歌舞伎年代記 全3冊
出版社:鳳出版
発行年:昭和51年(1976)

書名:狂言記の研究 全4巻5冊
著者:北原保雄・大倉浩
出版社:勉誠社
発行年:昭和58年(1983)

書名:評伝鶴屋南北 全2冊
著者:古井戸秀夫
出版社:白水社
発行年:平成30年(2018)
愛書館中川書房は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県など関東を中心に全国へ出張買取にお伺いしております(内容・量・地域によっては出張や買取りができない場合があります)。
当店の出張買取は予約制となっております。5000冊・10000冊規模の大量買取や遠方の出張買取、引越しや移転など期日のある際などはお早めに下記の買取専用フリーダイヤルへお電話ください。経験豊富な店主または店長がお伺いし買取りをさせていただきますので蔵書の整理は愛書館中川書房にお任せください。
【古書出張買取専用フリーダイヤル 0120-489-544】
![]()

※電話・メール相談の前に必ずこちらからご利用方法をご確認ください。
※一部商品において、お引取り等が出来ない商品もございますことをご了承ください。
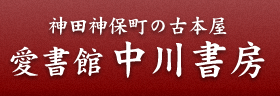
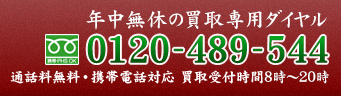


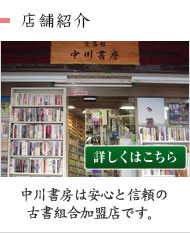
 by
by